全体の奉仕者
ドキュメンタリーアクティング|2022
筒 | tsu-tsu 板倉 勇人, 安齋 励應, 永楠 あゆ美
学習院大学
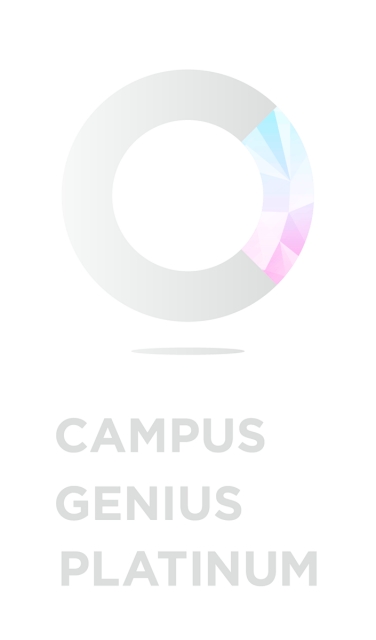
ART DIVISION PLATINUM
作品Webサイトhttps://drive.google.com/drive/folders/1lhAZhhIwzNZGrBR4cGSIWaqo41ANP5NG?usp=sharing
作者Webサイト https://twitter.com/ttsuth
森友問題で自死した赤木俊夫氏を演じゆく過程を公開した。ニュースで描かれる鬱になってしまってからの姿ではなく、ただ真っ直ぐでいただけ、そんな俊夫さんをそのまま受け入れていた雅子さん。2人の日常。続くことすらも許されなかったその日常から俊夫さんに近付きたいと思った。あらゆる人が、あらゆる立場からこの問題に関心を寄せるが、私にとって押しも引かれもしない原点は、「ある生が不条理に奪われた」ということのみである。その事、それを有耶無耶にしようとする臆病。私にも内在する、その臆病を私は乗り越えたかった。あらゆる分断が可視化された現代において、なお連帯を目指すのであれば、二項対立というアイデアそのものを考え直す必要がある。血糖値が急上昇すれば眠くなる。それを避けながら、場を開き続け、壁の存在をかなたにやること。遠くの他者を1人の人間として自らに引き寄せ想像するために、演技が可能にすることを信じている。 Photo by Ryu Ika




半透明のシートによって演者の姿はぼやけて、鑑賞者はその動きを細部まで見ることができない。そのため、作者自身が作品制作過程の取材においてそうしたように、鑑賞者も資料によって与えられた情報をもとに曖昧な細部をイメージして補完することになる。失われたものについて考えることを通じて作者と結び付けられた鑑賞者は、その重みを、シート越しにぼんやりとわかる演者の肉体の実在によって、はっきりと感じ取るのである。
「ドキュメンタリーアクティング」の手法を通じて、森友学園を巡る事件で自死された赤木俊夫さんにアプローチしようという試み。妻の雅子さんに取材を重ねてスクリプト化し、「赤木俊夫」を繰り返し演じる。趣味の落語を聞く時間、日常動作の癖。「事件の関係者」という括りでは見えてこないひとりの人間の営みが、作者の想像と思考と行動によって彫り出されていく。一方で、演じても演じても近寄りきれない「本人」の存在、伝えきれないもどかしさ。作品としての可能性と限界に向き合いつつ、テーマに対して体当たりで取り組んでいく、創作の熱量と真摯さに圧倒的な強度があった。ドキュメンタリーでも、裁判でもなく、アートにしかできない。生きていた、その人の体温を伝えられる作品である。